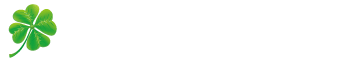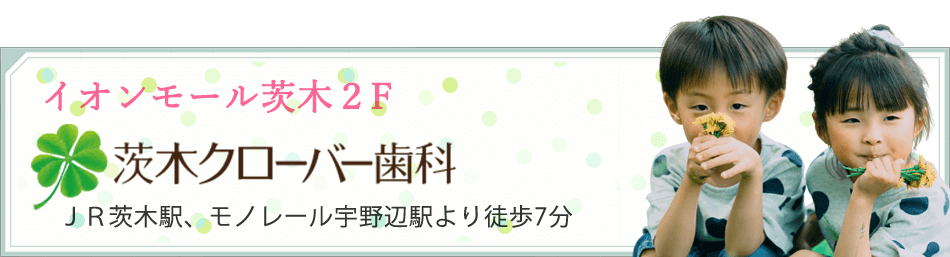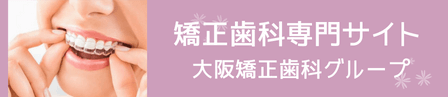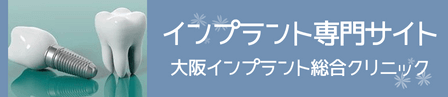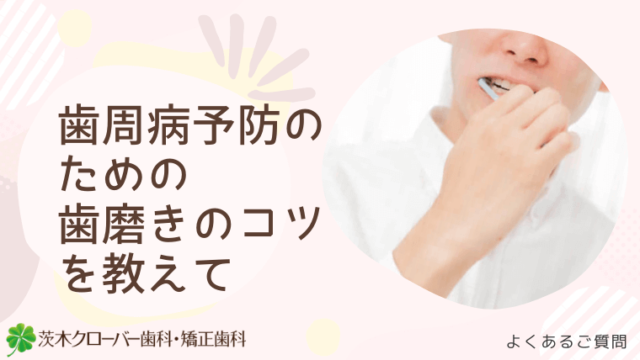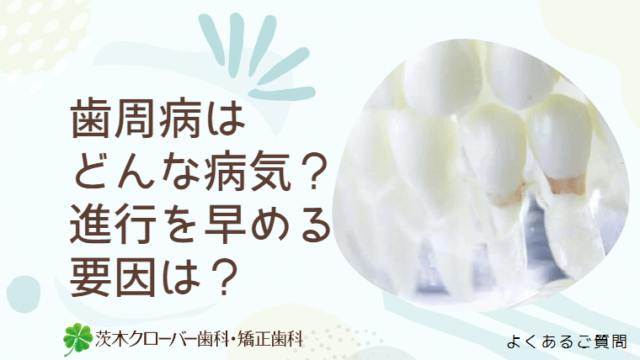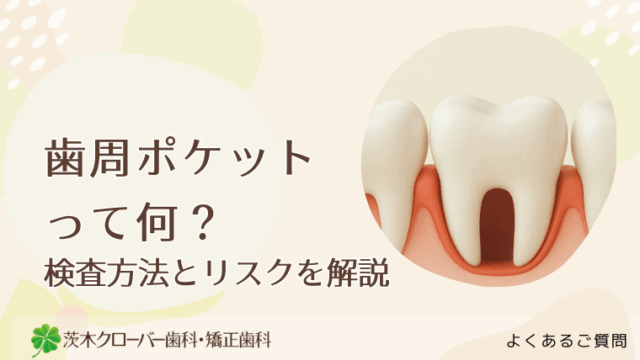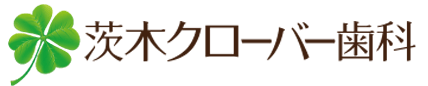歯ぎしりが歯周病を悪化させる?その関係と対策とは
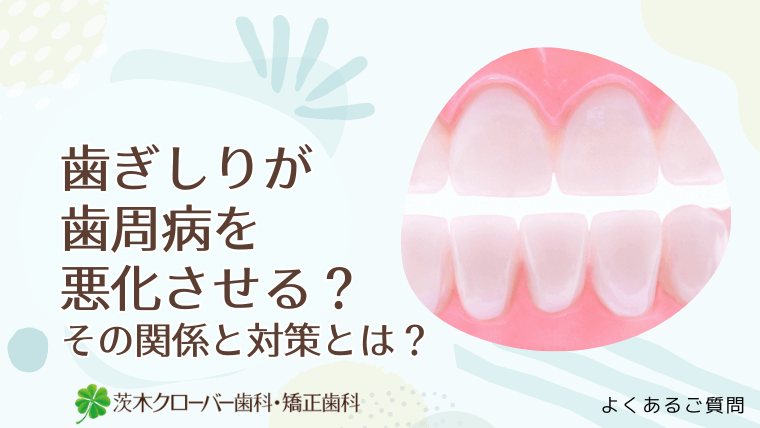
「歯ぎしりってクセみたいなものでしょ?」
「歯周病とは関係ないんじゃない?」
そう思っている方、実はけっこう多いんです。
でも実は、歯ぎしりは歯周病を進行させる“見えない敵”のような存在。
夜間の歯ぎしりが、知らず知らずのうちに歯ぐきや歯を支える骨にダメージを与え、歯周病の悪化に拍車をかけているケースも少なくありません。
このコラムでは、
- 歯ぎしりがどうして歯周病に影響するのか?
- どんなリスクがあるのか?
- そして、どう対策すればいいのか?
などについて、わかりやすく解説していきます。
「歯周病の治りが悪い」「最近歯がグラつく」そんなお悩みがある方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
目次
歯ぎしりは歯周病に悪影響を与えます
歯ぎしりは、歯ぐきや歯の周囲組織に強い負担をかけるため、歯周病が進行している方や初期の方にも悪影響を与える可能性があります。
歯ぎしりは歯周病を悪化させる原因になり得ます。
歯周病は歯ぐきや歯を支える骨がダメージを受ける病気。一方、歯ぎしりは無意識のうちに歯に強い力をかけるクセです。これが重なると、歯周組織へのダメージが倍増します。
なぜ歯ぎしりが歯周病を悪化させるのか?
歯ぎしりによって歯や歯ぐきに強い負荷が継続的にかかることで、炎症が起きている歯周組織がさらにダメージを受け、歯周病が進行しやすくなります。これは、力のかかり方が「噛む」動作とは異なり、異常で不規則な負荷だからです。
歯ぎしりの圧力が、炎症を起こしている歯周組織をさらに壊してしまいます。
歯ぎしりの圧力は“ケタ違い”
歯ぎしりのときにかかる力は、自分の体重以上ともいわれる強さで、しかもそれが長時間・繰り返し続くのが特徴です。
この力が歯ぐきや歯槽骨(歯を支える骨)にかかると、以下のような悪影響が起こります。
- 歯槽骨の吸収が加速する
→ 歯周病によって炎症が起きているとき、そこに歯ぎしりの強い圧力が加わることで、骨の破壊が進行しやすくなります。 - 歯周ポケットが深くなる
→ 不安定な歯の動揺が続くと、歯ぐきとの隙間(歯周ポケット)がさらに深くなり、歯垢や細菌がたまりやすい環境に。 - 炎症の範囲が広がる
→ 負荷がかかる部位を中心に、周囲の歯ぐきにも炎症が波及しやすくなります。
「治ろうとする力」を妨げる存在
実は、歯周病の治療中は歯ぐきや骨が再生しようとする力が働きます。でもその途中で歯ぎしりによる物理的な負荷が加わると、治癒が妨げられてしまうのです。
たとえるなら…
傷口を治しているときに、何度もこすったり叩いたりしていたら、治るものも治りませんよね。それと同じように、歯ぎしりは歯周病治療の邪魔をしてしまう存在なんです。
噛み合わせのズレ→力の偏り→さらなる悪化
歯ぎしりが習慣化すると、噛み合わせのバランスが乱れます。
その結果、特定の歯や部位にばかり力が集中してしまい、そこにある歯周組織が集中攻撃を受けるような形になってしまいます。
力の偏りは、炎症の偏りや進行スピードの差につながり、歯周病のコントロールが難しくなる要因に。
歯ぎしりは単なる「クセ」や「ストレス反応」では済まされない、歯周病の進行を加速させるリスク因子です。
特に初期~中等度の歯周病の段階では、早めに歯ぎしりに気づき、対策を取ることで、将来的な歯の喪失リスクをぐっと下げることができます。
特に歯周病により骨が溶けはじめている状態では、歯を支える力が弱くなっているため、歯ぎしりの圧力でさらに歯が動揺しやすくなります。これは、歯の寿命を縮めるリスクにつながるため注意が必要です。
歯ぎしりによる具体的な影響とは?
歯ぎしりが続くと、歯周病が進行しやすくなるだけでなく、歯自体や被せ物・詰め物にも悪影響を及ぼします。
歯ぎしりは歯にも被せ物にもダメージを与えます。
具体的な影響を以下にまとめます。
- 歯がグラグラする
→ 歯周病により支える骨が減っている状態では、歯ぎしりの圧力で歯が動いてしまいます。 - 被せ物や詰め物が割れたり外れたりする
→ 異常な力が長期間かかることで、修復物が破損することがあります。 - 歯ぐきの炎症が悪化する
→ 摩擦や力の加わり方が不均等になり、炎症が治まりにくくなります。 - あごの筋肉に負担がかかる
→ 顎関節症のリスクも高まるため、口全体のバランスが乱れる原因にもなります。
その結果、歯ぎしりが歯周病だけでなく、全体的な口腔環境を悪化させてしまうことがあるのです。
歯周病と歯ぎしり、どちらも対策が必要です
歯周病と歯ぎしりはお互いに悪影響を及ぼし合うため、どちらかだけを治しても根本的な改善は難しくなります。
両方を同時にケアするのが大切です。
どちらか一方を放置すると、もう一方の症状も改善しにくくなります。たとえば、歯周病の治療だけ行っても、歯ぎしりを放置していれば再び組織が傷つきやすくなり、治癒が遅れたり再発したりすることがあります。
歯ぎしり・歯周病を予防するためにできること
セルフケアと歯科医院でのサポートを組み合わせることで、歯周病と歯ぎしりの悪循環を防ぐことができます。
予防には日常のケアと専門的な治療の両立が重要です。
以下のような対策が効果的です。
- 丁寧な歯磨きと歯垢の除去
→ 正しい歯磨きで歯垢をしっかり除去することで、歯周病の進行を防ぎます。 - 定期的な歯科での健診とクリーニング
→ 早期発見・早期治療で悪化を防ぎます。 - マウスピースの使用(ナイトガード)
→ 歯ぎしりによる力の分散や、歯の摩耗防止に役立ちます。 - ストレスマネジメント
→ 歯ぎしりはストレスと関係することが多く、睡眠や生活習慣の見直しも効果的です。
これらを実践することで、歯周病と歯ぎしりの連鎖を断ち切ることが可能になります。
歯ぎしりの兆候に気づくポイントとは?
歯ぎしりは寝ている間に無意識に行われることが多いため、自覚しにくいのが特徴です。以下のようなサインに気づいたら、歯科医院で歯が擦り減っていないか相談してみましょう。
日常の「ちょっとした違和感」がサインです。
- 朝起きたときにあごが疲れている
- 歯がすり減って平らになっている
- 被せ物や詰め物がよく外れる
- 家族に「寝てる時に歯ぎしりしてたよ」と言われた
こういったサインに気づいたら、マウスピースや対処法を歯科医院で相談しましょう。
歯ぎしりと歯周病悪化の関係に関連するQ&A
歯ぎしりは歯周病を悪化させる原因になり得ます。歯ぎしりは、歯ぐきや歯の周囲組織に強い負担をかけるため、歯周病が進行している方や初期の方にも悪影響を与える可能性があります。
口腔検査の主な目的は、虫歯や歯周病、口腔内の異常を早期に発見し、適切な診断・治療計画を立てるためです。また健康な歯を維持するための予防策や、全身の健康管理にも役立ちます。
唾液検査では、虫歯や歯周病のリスク評価、唾液の分泌量やpH値(酸性度・アルカリ性度)、お口の中の細菌数や清潔度などが分かり、口臭の原因やお口のトラブル予防・早期発見にもつながります。
歯周ポケット検査は、歯と歯ぐきの隙間(ポケット)の深さや出血の有無を専用の器具で測り、歯周病の進行度や炎症の有無を調べる検査です。自覚症状がなくても歯周病リスクを評価できます。
検査の内容や目的をしっかり理解してもらうことで、患者が検査の必要性を納得し、安心して治療に臨んでもらうためです。科学的根拠に基づく正確な診断と医療安全の確保にもつながります。
まとめ
歯周病と歯ぎしりは早めのケアが大切です
歯ぎしりと歯周病は、どちらか一方だけでなく、お互いに影響しあう厄介な組み合わせです。
「歯周病の治りが悪いな…」「歯がグラつく気がする…」と感じたとき、そこに“歯ぎしり”が関係している可能性もあります。
だからこそ、セルフケアだけでなく、歯科医院での早めの相談・ケアがとっても大切!
マウスピースの装着や、歯周病の専門的な治療をうまく組み合わせて、長く健康な歯を保ちましょう。