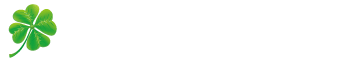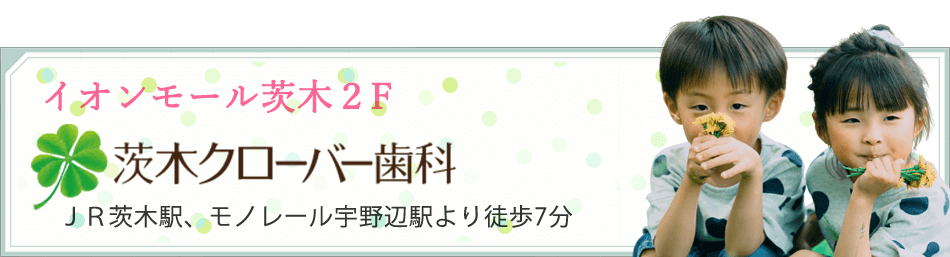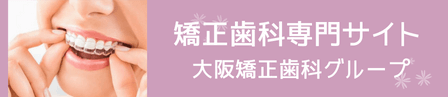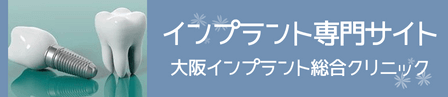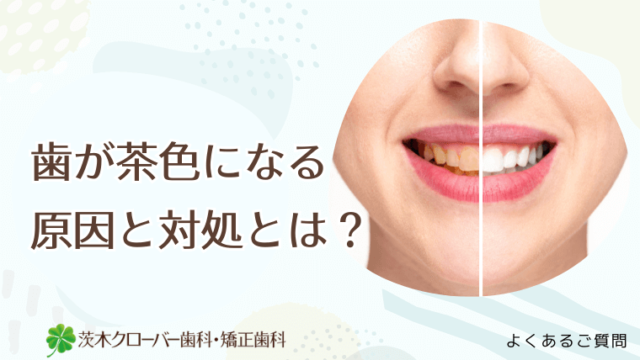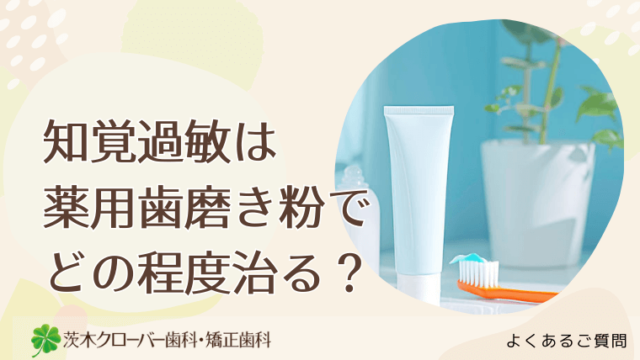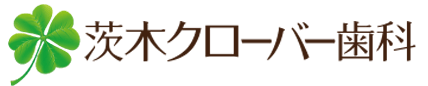歯の磨きすぎはダメですか?歯や歯茎へのダメージと改善方法について
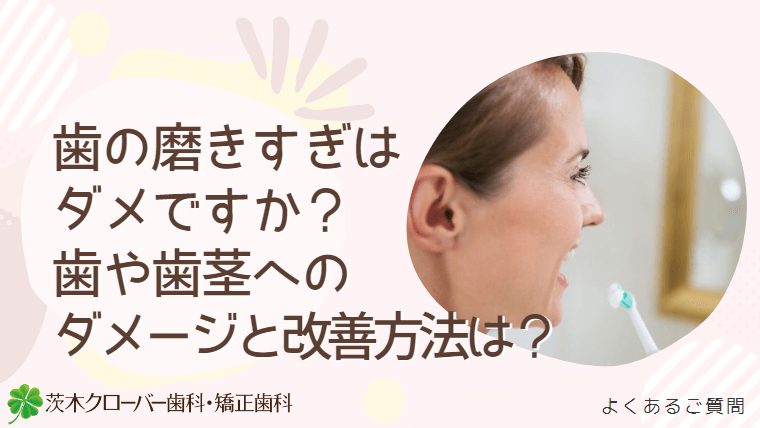
虫歯予防や歯周病予防のために歯磨きはとても重要ですが、歯の磨きすぎはオーバーブラッシングと呼ばれ、歯や歯茎にトラブルが起こってしまいます。歯の磨きすぎでどんなことが起こるのか、どう対処すればいいのかについてご説明します。
目次
歯の磨きすぎ=オーバーブラッシングの症状とは?

歯の磨きすぎによって歯や歯茎に何かしらの症状が出てトラブルが起こることを「オーバーブラッシング」といいます。オーバーブラッシングには、いくつかの典型的な症状があります。
知覚過敏が起こる
歯ブラシを歯に強くあてすぎたり、擦りすぎたりすることで、歯の表面のエナメル質が削られてしまい、象牙質がむき出しになって知覚過敏が起こります。
知覚過敏になると、歯に歯ブラシの毛先が触れたり、歯に風があたっただけでも痛みを感じます。その他には、冷たいものや甘いものを飲食した時に痛みます。
知覚過敏の痛みはほんの数秒だけ起こり、継続する痛みではありませんが、何度も繰り返し起こります。
歯茎が分厚くなってしまう
歯ブラシで歯茎を擦り過ぎると、その刺激によって歯茎が分厚くなってしまいます。これを歯肉の肥厚(フェストゥーン)といいます。子供への仕上げ磨きをやり過ぎた時にも起こります。歯ブラシは軽く持ち、力を入れて擦り過ぎないように注意しましょう。
歯茎の退縮が起こる
歯茎の退縮とは、歯茎が痩せて下がってしまうことです。歯茎が痩せたときは、歯周病が疑われますが、歯周病以外の原因として、歯を力を入れてブラッシングし過ぎたということもあります。
歯ブラシの毛先が強く当たると、歯茎に傷がついて退縮が起こります。その結果、歯茎に埋まっていた象牙質の部分が露出してしまい、同時に虫歯や知覚過敏が起こる可能性があります。
歯ぐきから出血する
歯茎から出血があると歯周病かと不安になると思いますが、歯を強く磨きすぎたために出血が起こることもあります。どのような原因で歯ぐきからの出血が起こっているのかは、歯科医院での定期健診でわかります。
歯周病が原因の場合は、悪化させないためにすぐに歯周病治療に入る必要があります。
歯の磨きすぎによるエナメル質の損傷

1. エナメル質の役割とは
エナメル質は、歯の最も外側にある非常に硬い層で、歯を保護する役割を持っています。エナメル質は人体で最も硬い組織であり、食べ物や飲み物からの酸や、噛む力から歯を守ります。また、虫歯の原因となる細菌が歯に侵入するのを防ぐためにも重要です。しかし、エナメル質は再生能力を持たないため、一度損傷すると元に戻ることがありません。
2. 歯の磨きすぎがエナメル質に与える影響
エナメル質は非常に硬いものの、物理的な摩耗には弱く、過剰なブラッシングや硬い歯ブラシを使用することで徐々に削れていきます。特に、歯を強く磨くことで摩擦が増し、表面のエナメル質が薄くなる可能性があります。これが進行すると、以下のような問題が発生します。
知覚過敏の原因
エナメル質が削れることで、下にある象牙質が露出し、冷たい飲み物や熱い食べ物を摂取する際に歯がしみる「知覚過敏」の症状が現れることがあります。
虫歯のリスク増加
エナメル質は虫歯菌が歯に侵入するのを防いでいますが、磨きすぎでエナメル質が薄くなると、歯がより虫歯にかかりやすくなります。
歯の見た目の変化
エナメル質が削れると、歯の表面が不均一になり、見た目にも影響が出ることがあります。また、歯の色がくすんで見えることもあります。
3. エナメル質の損傷が引き起こす症状
エナメル質が損傷すると、以下のような症状が現れることがあります。
冷たいものや熱いものに対しての過敏症
エナメル質が損傷し象牙質が露出すると、歯の神経に直接刺激が伝わりやすくなり、痛みやしみる感覚が強くなります。
歯の表面がザラザラする感覚
エナメル質が削れた部分は滑らかではなく、指や舌で触るとザラザラした感じがすることがあります。
歯の透明感の増加
エナメル質が薄くなると、歯の端が透明に見えることがあり、これはエナメル質の減少による典型的な兆候です。
4. エナメル質の損傷を防ぐための対策
エナメル質を守るためには、以下の対策が有効です。
適切なブラッシング方法を習得する
強く磨くのではなく、優しく小さな円を描くようにブラシを動かすことで、歯やエナメル質への負担を軽減します。電動歯ブラシを使用する際も、力を入れすぎないことが重要です。
柔らかい歯ブラシを使用する
硬い歯ブラシはエナメル質にダメージを与えやすいので、歯や歯茎に優しい「柔らかめ」の歯ブラシを選びましょう。
フッ素配合の歯磨き粉を使用する
フッ素はエナメル質を強化し、酸による損傷を防ぎます。フッ素配合の歯磨き粉を使うことで、エナメル質の損傷を予防しやすくなります。
酸性の飲食物に注意する
酸性の飲み物(炭酸飲料、柑橘系ジュースなど)や食べ物を頻繁に摂取すると、エナメル質が弱くなります。これらを摂取した後はすぐに歯を磨かず、口を水でゆすぐと良いでしょう。
5. エナメル質が損傷した場合の治療方法
エナメル質が損傷した場合、完全に元に戻すことはできませんが、歯科治療によって症状を和らげることが可能です。例えば、次のような治療法が考えられます。
フッ素塗布
歯科で行われるフッ素塗布は、エナメル質の再石灰化を促進し、さらに進行することを防ぎます。
レジン充填
エナメル質が損傷している部分にレジンを埋め込むことで、象牙質を保護し、知覚過敏を軽減することができます。
エナメル質は歯を保護する最前線のバリアであるため、磨きすぎによるダメージを防ぐことが重要です。
歯の磨きすぎを防ぐためには?
歯の磨きすぎを防いで知覚過敏や歯茎の退縮を予防するためにはいくつかのポイントがあります。
歯ブラシの選び方

歯ブラシは種類が豊富で、ヘッドの大きさや形や毛の硬さなどの違いによって、様々なものが販売されています
サイズは小さい方が歯全体にブラシの毛先が届きやすいといえます。毛の硬さに関しては、硬い方が汚れを落とすには効果的ですが、強い力で使用すると歯や歯茎を削って傷つける恐れがありますので、硬さが普通のものを選びましょう。
歯茎に炎症が起こっている場合は、軟らかめの歯ブラシを選びます。ただし、毛先が柔らかいと、汚れを落とす能力が劣りますので、時間をかけて丁寧に歯磨きする必要があります。
あなたはオーバーブラッシングではないですか?
以下の項目に当てはまる方は、オーバーブラッシングかもしれません。歯科医院の定期健診で歯科衛生士が歯を診るとオーバーブラッシングかどうかわかります。
- 虫歯じゃないのに歯がしみる
- 歯が長くなったような気がする
- 力を入れて磨かないときれいにならないと思っている
- 硬い歯ブラシを好む
- 歯磨き指導を受けたことがない
- 新しい歯ブラシが2週間位で開いてしまう
歯ブラシの寿命は?
歯ブラシの寿命は1ヶ月程度と考えましょう。1ヶ月経っていなくても、毛先が開いてしまった歯ブラシはすぐに取り替えましょう。適切な磨き方が出来ていない場合、歯ブラシの寿命を極端に縮めてしまっていることもあります。

上の写真のように、ブラシの毛先全体が外側に向かって開いていたり、ブラシの一部の毛が完全に窪んでしまっている場合は、歯磨きの時に力が入り過ぎていて歯ブラシを歯に押し付けてゴシゴシと磨いていることが考えられます。
強い力で歯を磨くと、歯の表面のエナメル質が削れて傷つけてしまったり、エナメル質が薄くなったり、歯茎にブラシの毛先が当たってその刺激で歯茎が退縮して下がってしまい、結果的に知覚過敏を起こすことがあります。また、しっかりと擦っている割には細かい汚れがきれいに落ちていないこともあります。歯磨きの際には、歯ブラシを鉛筆持ちにして軽い力でブラッシングしましょう。
研磨剤の入っていない歯磨き剤を選ぶ
ドラッグストアに行くと、様々な薬効成分の入った歯磨き剤が並んでいて、どれが良いのか迷われる方が多いと思います。
歯の磨きすぎを防ぐためには、リン酸カルシウムなどの研磨剤が含まれていない歯磨き剤を選んで、歯や歯茎が擦り減るのを防ぎましょう。
歯の磨きすぎによる歯や歯茎へのダメージに関するQ&A
オーバーブラッシングの症状には、知覚過敏や歯茎の退縮、歯ぐきからの出血などがあります。
オーバーブラッシングかどうか判断するには、虫歯以外の理由で歯がしみる、歯が長くなったような感じがする、力を入れないときれいにならないと感じるなどの症状に注目することがあります。
歯の磨きすぎを防ぐためには、適切な歯ブラシの選択や正しい磨き方が重要です。また、歯磨き剤には研磨剤の入っていないものを選ぶことも助けになります。
まとめ

歯磨きのしすぎで歯や歯茎にトラブルが起こることがあります。歯磨きで起こっている症状は、歯磨きの仕方を変更することで改善させることが出来ます。歯医者の定期健診にお越しいただければ、歯磨きの強さが適切かどうかわかりますし、正しい歯みがきの仕方を知るきっかけにもなります。