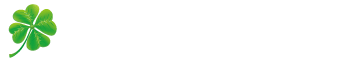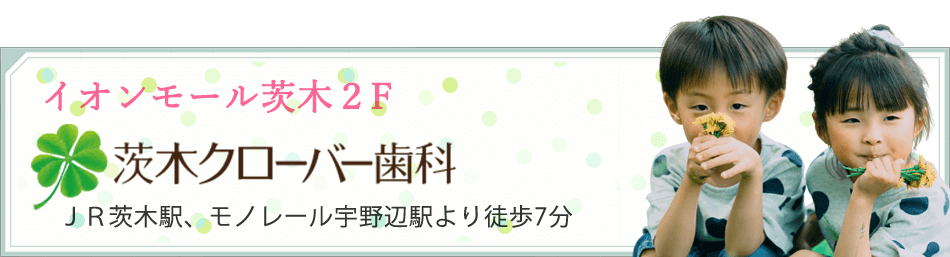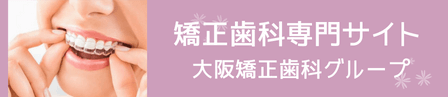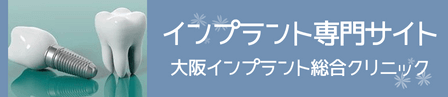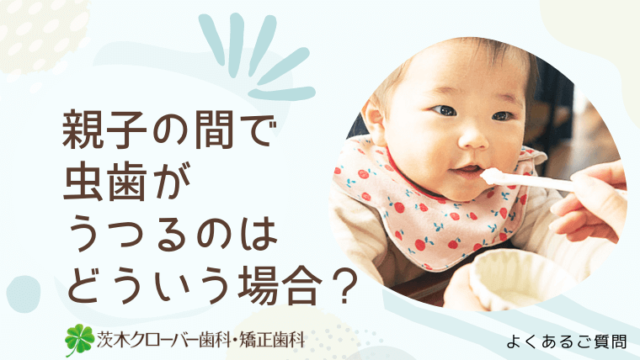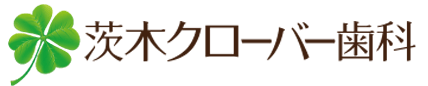日本の子どもの8割が口呼吸って本当?

近年、日本で口呼吸の子どもが増えており、8割にものぼると言われています。なぜそれ程口呼吸の子どもが多いのか、どのような理由で口呼吸になるのかをご説明します。
目次
口呼吸の子供の割合は8割
2021年に新潟大学で全国の小児歯科医を対象に行われた研究では、日本の子供たちの31%が日常的にお口ぽかんと呼ばれる状態で口呼吸をしているということがわかりました。
ほんの僅かに口が開いている状態の子供を含めると、子供の約8割が口呼吸になっているといわれています。
口呼吸が原因で噛む、飲み込むことがうまく出来ない子どもが増えている
子どもの口呼吸は、今や日本全体の問題になってきています。食べる、飲む、話すといった口腔機能が発達または機能していない状態を口腔機能発達不全性といいますが、口呼吸が原因で口腔機能発達不全性を発症する子どもたちが日本で増えている傾向があるからです。
多くの子どもたちが、鼻呼吸が出来ないせいで、病気ではないのに食べ物を噛む、飲み込むという基本的なお口の機能がうまく働いていないということになります。
口呼吸が歯並びに与える影響
口呼吸が子どもの歯並びや顎の発達に悪影響を及ぼすことが多いです。口呼吸は、歯列が狭くなったり、出っ歯や開咬といった不正咬合のリスクを高める要因となります。このため、口呼吸の矯正は早期に取り組むことが推奨されます。
- 出っ歯(上顎前突)の原因となる
- 顎が十分に発達せず、歯列が狭くなる
- 歯が重なって生える(叢生)
- 開咬(上下の前歯が噛み合わない状態)のリスクが増す
- 顔つきや口元の見た目に影響が出る
口呼吸は、早期に改善することが重要です。
口呼吸の身体への影響は?

では、口呼吸をすることによってどんな影響があるのでしょうか?
- 唾液が乾燥してドライマウスになる
- 虫歯、歯周病になりやすい
- 唇の力が弱くなり歯並びが悪くなる
- 花粉症、アレルギー性鼻炎になりやすい
- 風邪、インフルエンザになりやすい
- いびきをかき、睡眠の質が低下する
このように、口呼吸にはデメリットしかありません。
口腔機能低下症に保険が適用されることになった
口腔機能低下症はもともと高齢者に多い症状の一つで、食べ物を噛んだり飲み込んだりする
ことが難しい状態のことをいいます。
高齢者増加の影響もあり、口腔機能低下症がみられる人が増え、医療費の増加の原因の一つとなっています。問題は、口腔機能がうまく発達せず、噛んだり飲み込んだりするのが難しいという症状が、子どもたちの間でみられることです。
子どもたちがこのまま成長すると口腔機能の低下による将来の医療費負担の増加することが予想されます。
2018年の診療報酬改定で、国は口腔機能低下症、口腔機能発達不全性を正式に病気として指定し、保険が適用されることを決定しました。国は子どもに対する口腔機能訓練を推奨し、何とか食い止めたいと考えているからです。
実際の訓練を効率的に行うには、子どもの口呼吸を防ぎ、よく噛めるようにするために何が大切かを保護者の方に十分理解していただく必要があります。
口呼吸になってしまう4つの理由
口呼吸になってしまう理由は、舌やお口の周りの筋肉が十分に発達していないことが考えられます。そのために口呼吸になってしまう理由は次の4つです。
- 離乳食を与える時期が早い
- 前歯で噛ませていない
- 口腔機能の発達を狙った食事がなされていない
- 鼻で息ができないことを理由に、鼻で呼吸をさせていない
口呼吸をどうやって鼻呼吸に変えるの?
口呼吸になっている理由がわかれば、おのずから解決策もわかります。しかし口呼吸が習慣になっているお子さんを鼻呼吸に変えるのは、それほど簡単なことではありません。
口呼吸のお子さんは舌の位置が低くなっている場合が殆どなので、歯科では舌の位置を正常に戻すためのマウスピースを就寝中に使って頂き、同時にお口の周囲の筋肉を鍛えるための、ご自宅ですぐに出来るお口周りの体操の指導も行っています。
1. 舌のポジショニングトレーニング
舌が正しい位置にあることが、鼻呼吸を促進し、口呼吸の改善に役立ちます。舌の位置は上あごに軽くつけた状態が理想です。この状態を保つトレーニングを行うことで、自然に鼻呼吸が促されます。
- 方法・・舌を上あごにくっつけ、口を閉じた状態を数分維持します。1日に数回、意識的に行うことで徐々に習慣化させます。
2. 鼻呼吸を意識する呼吸トレーニング
呼吸の方法を意識的に改善するためのトレーニングです。鼻呼吸に慣れていない人は、まずはゆっくりと鼻から吸って鼻から吐く呼吸法を習慣づけます。この方法は、リラックス効果もあり、呼吸の改善に役立ちます。
- 方法・・背筋を伸ばしてリラックスした状態で、鼻からゆっくり深く息を吸い込み、そのまま鼻から息を吐き出します。この動作を1回につき5分程度、1日数回繰り返します。
3. 口の筋力を鍛えるエクササイズ
口周りの筋力が弱いと、口が開きやすくなり、口呼吸になりがちです。口の周りの筋肉を鍛えるエクササイズを取り入れることで、口を閉じた状態を保ちやすくします。
- 方法・・唇をしっかり閉じて、10秒間その状態を維持します。その後、唇をリラックスさせる。この動作を1日に10回繰り返します。
4. 鼻詰まりを解消するためのエクササイズ
鼻呼吸が困難な場合、鼻の通りを良くするためのエクササイズを行うことが重要です。鼻腔が詰まりやすい場合でも、定期的に鼻呼吸の練習をすることで改善が期待できます。
- 方法・・息を止めた状態で鼻をつまみ、頭を前後にゆっくりと動かします。息が苦しくなる前に鼻から息を吸い、鼻呼吸を再開します。このエクササイズを繰り返すことで、鼻の通りが良くなることがあります。
5. 鼻呼吸を促進するテープ療法
就寝時に無意識に口呼吸になってしまう場合は、口に専用のテープを貼って強制的に鼻呼吸を促す「口閉じテープ」が有効です。これにより、鼻呼吸の習慣化を助けます。
- 方法・・寝る前に専用のテープを口に貼り、無理なく鼻呼吸ができる状態を維持します。初めて使用する場合は、専門家の指導を受けると安心です。
6. 正しい姿勢を意識する
姿勢の悪さは口呼吸につながることがあります。頭が前に突き出した「猫背」姿勢は、口が開きやすくなるため、背筋を伸ばして正しい姿勢を意識することが大切です。
- 方法・・壁に背中をつけて立ち、頭・肩・お尻を壁に軽くつけたまま、深呼吸を行います。この姿勢で呼吸することで、鼻呼吸を習慣づけやすくなります。
これらのトレーニングを日常生活に取り入れることで、口呼吸の改善が期待できます。ただし、長期間口呼吸が続いている場合や、鼻の異常がある場合は、医師や歯科医に相談して専門的な治療を受けることも重要です。
子供の口呼吸に関するQ&A
近年、口呼吸の子どもが増えており、8割にものぼると言われています。
口呼吸には唾液の乾燥、虫歯や歯周病のリスクの増加、歯並びの悪化、花粉症やアレルギー性鼻炎の発症リスクの増加、風邪やインフルエンザの感染リスクの増加などがあります。
口呼吸を鼻呼吸に変えるのは容易ではありませんが、舌の位置を正常に戻すためのマウスピースや口腔周囲の筋肉を鍛えるための体操などが効果的です。
まとめ

日本の子供の8割が口呼吸になっていることには、国も問題にしています。口腔機能発達不全性の子供たちが高齢になった時、口腔機能低下症が深刻な状態になる可能性が高いからともいえます。
それを防ぐために、今後は歯科医師も子どもたちの口腔の育成に懸命に取り組んでいくことになります。歯科医院では、舌の位置を正常な位置に戻すためのマウスピースや、口腔周りのご自宅で出来る簡単な体操の普及にも取り組んでいます。