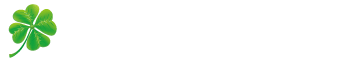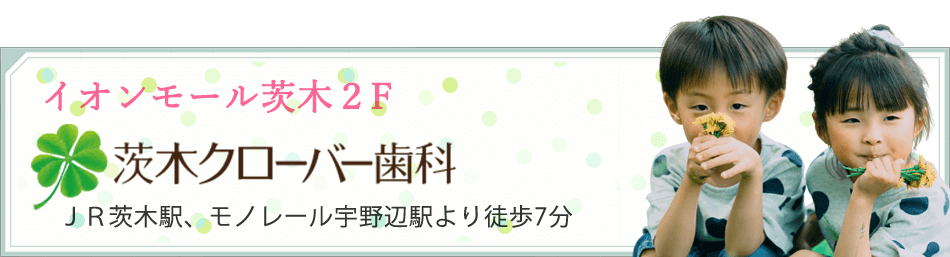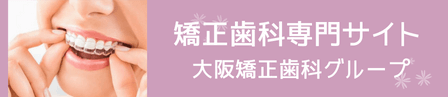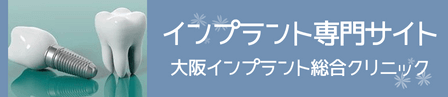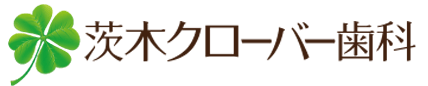子どもの指しゃぶりは歯並びを悪くするの?
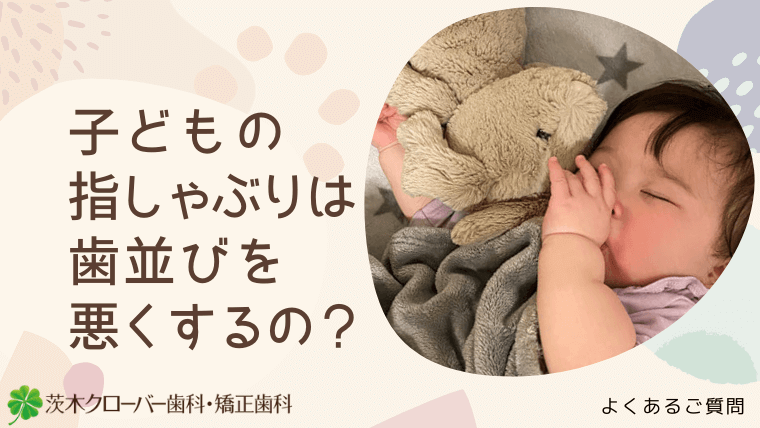
子どもの指しゃぶりは、3歳頃までなら大きな心配はありませんが、4歳以降も続くと歯並びやかみ合わせ、あごの成長に悪影響を与えることがあります。永久歯への生え変わりや将来的な不正咬合のリスクを減らすため、できるだけ早い段階で指しゃぶりの習慣を卒業させることが大切です。
この記事を読むとわかること
- 指しゃぶりが歯並びへ及ぼす具体的な影響
- よく見られる不正咬合の種類(開咬・出っ歯・叢生など)
- 年齢ごとに異なる影響の出やすさとリスク
- 指しゃぶりの主な原因と子どもの心情
- 無理なくやめさせるための具体的なアドバイスや対策
- 保護者が気をつけるべきサインとサポートのコツ
「自然に治るだろう」「小さいうちは大丈夫?」と迷われているご家庭へ――正しい知識と見守りのポイントをわかりやすく解説します。お子さんの歯と健康な成長のために、今日からできる工夫を一緒に考えましょう。
目次
子どもの指しゃぶりは歯並びを悪くする
子どもの指しゃぶりというのは、歯列に影響を与えるという点で好ましい習慣ではありません。5才を過ぎても指しゃぶりを止められない子どもは、アゴの骨格形成に影響を与えることがあり、永久歯に生え変わるときにも、歯並びが悪くなってしまうことがあります。
長く癖が続くと、乳歯の歯並びだけでなく、永久歯が生えてくる位置やあごの成長にも影響が出ることがあります。たとえば「前歯でうまく咬めない」「発音が不明瞭」と悩まれて来院された方もいらっしゃいました。早めに気づき対応できた場合、簡単なアドバイスや口腔体操だけで改善し、矯正治療を回避できた例もあります。
指しゃぶりによる歯並びへの影響
指しゃぶりによって指で前歯を押す癖がついてしまうと、様々な不正咬合を引き起こします。代表的なものは下記の4種類です。
- 指しゃぶりを続けると、奥歯はかみ合っていても前歯がかみ合わなくなる開咬(かいこう)になる
- 指しゃぶりをしながら前歯を前に押し続けると、上の前歯が前に出てしまう上顎前突(じょうがくぜんとつ)、いわゆる出っ歯になる
- 逆に指しゃぶりで下の前歯を押し続けると、歯並びのアーチが狭くなって歯がきれいに並ばず叢生(そうせい)、いわゆるガタガタの歯並びになる
- 指しゃぶりで歯を右か左かの一定方向に押し続けると、上下の奥歯が横にずれて中心があわない片側性交叉咬合になる
指しゃぶりは単なる癖に見えますが、長期間続くと、舌や唇、頬の筋肉の働きに影響が出て、歯に異常な力がかかります。この力が前歯を押し出したり、上下の歯が噛み合わなくなる「開咬(かいこう)」を引き起こす主な原因の一つです。歯並びが悪くなると、食べ物をうまく噛めなかったり、言葉の発音にも影響が出やすくなります。
指しゃぶりは3才までなら歯並びへの影響は殆どない
3才児の歯は乳歯の段階で、まだ永久歯に生え替わっていません。この段階では、指しゃぶりで歯並びが悪くなることはあまりありませんし、永久歯の歯並びに影響を与えることもあまり考えられません。
一般的には子供の指しゃぶりを放置しておいても、成長するにつれて自然にしなくなるのですが、3才を過ぎても指しゃぶりが続いている子に対しては、大人が注意して見てあげて指しゃぶりをやめさせるようにしなければなりません。
4才を過ぎると子供の自我が芽生えてきますので、大人が指しゃぶりに癖をやめさせようとしても、なかなかなおらない場合があります。そのため、指しゃぶりは4才までには必ずなおすようにしましょう。
指しゃぶりの期間と頻度が問題に
短期間の指しゃぶりであれば、歯並びに大きな影響を与えることは少ないですが、3歳以降も頻繁に続けている場合は注意が必要です。特に4~5歳になっても指しゃぶりが続くと、永久歯が生える時期に影響が及び、歯並びの問題が固定化しやすくなります。
指しゃぶりの原因

子供の指しゃぶりの原因は、大きく2つあります。
1. 眠気
子供は眠くなると心を安らげるために、お母さんのおっぱいを呑んでいる状態と同じような状況を求めます。そこで、お母さんのおっぱいに代わるものとして自分の親指を使います。親指は、お母さんの乳首と大きさが同じくらいで、しかも簡単に口に運べて吸いやすい形状をしています。
2. 寂しさ
寂しくなると、遊び相手や話し相手が欲しくなります。ですが、相手が居ないと精神的に少し不安定になります。心のすき間を埋めるために指しゃぶりをして落ち着こうとするのです。一種の精神安定剤の役割といえるでしょう。
この2つが原因で共通しているのは、子どもが心を落ち着かせたい、安らぎたいと思っているときに無意識のうちに指しゃぶりが起きてしまっているということです。
ちなみに、子どもがまだお母さんの胎内にいるときから、実は指しゃぶりが始まっていることが明らかになっています。
子どもの指しゃぶりを止めさせるには
習慣化してしまった子どもの指しゃぶりをやめさせるには、子どもの生活のリズムを整えて,外遊びや運動によって体力を使わせ、しっかりと発散させたり,親が子どもに対して、よりスキンシップを図るようにするということが必要だという見解が、小児科と小児歯科の保健検討委員会によってまとめられていますので、ご紹介します。
指しゃぶりは、赤ちゃんが母乳やミルクを飲む動きと似ており、安心感を得る行動の一つです。ストレスや疲れ、不安を感じているときに指しゃぶりが多くなることもあります。単に「悪い癖」として叱るのではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら、楽しくやめられる方法を探ることが長続きのコツです。
無理なくやめさせるための具体的対策例
- ポジティブな声かけを大切にする
→「もう大きくなったからできるね」「すごいね、今日は指しゃぶりしなかったね」と褒めてあげることで自己肯定感が育ち、やめる意欲がわきます。 - 生活習慣や環境の見直し
→ストレスを感じやすい場面や寝る前に指しゃぶりが増える場合は、安心できる声かけやお気に入りのぬいぐるみを用意するなど代替行動を促す工夫を試しましょう。 - 視覚的な「卒業カレンダー」やシール表を活用
→子ども自身が進捗を感じられる工夫で、達成感を得ながら習慣を変えていけます。
保護者が注意すべきサインと相談のタイミング
もし4歳を過ぎても指しゃぶりが続き、以下のような兆候が見られる場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
- 上の前歯が極端に前に出てきた
- 発音が不明瞭になってきた
- あごの成長に左右差や変形が疑われる
- 指しゃぶり以外に口周りの癖(口呼吸、舌突出癖)がある
歯科医師や小児矯正の専門家は、お子さんの成長に合わせて最適なアドバイスやサポートを行います。早期介入が将来的な矯正治療の負担軽減につながるため、気になることがあれば遠慮なく受診しましょう。
家庭でのケアと歯科医院でのサポートを連携させる
家庭でのポジティブな取り組みと、定期的な歯科検診を組み合わせることが、指しゃぶりから生じる歯並びの問題を予防・早期発見に役立ちます。矯正装置の必要性の有無を含め、専門家の診断を受けながらお子さまに最適な成長を促していくことが重要です。
子どもの指しゃぶりと歯並びに関するQ&A
子どもの指しゃぶりは歯並びに悪影響を及ぼします。指で前歯を押す習慣が歯列に不正咬合を引き起こし、開咬、上顎前突、叢生、片側性交叉咬合などの問題をもたらします。
5才を過ぎても指しゃぶりを続けると、アゴの骨格形成に影響を与え、永久歯が生え変わる際に歯並びが悪化する可能性があります。
子どもの指しゃぶりをやめさせるためには、生活のリズムを整えて外遊びや運動で体力を使わせ、スキンシップを増やすことが重要です。親が子どもに寄り添い、精神的な安定感を提供することが役立ちます。
まとめ

指しゃぶりを続けると、噛み合わせや歯並び、発音などに影響を与えます。なるべく4才になるまでには指しゃぶりの癖をなおしましょう。